
私は自律型海中ロボット(AUV)を用いた海洋生物の自動追従に関する研究を行っています。本手法では、ソナーやカメラで得られた情報から機械学習により海洋生物を発見するため、バイオロギングのような事前の捕獲を必要とせず、深海生物の観察も可能です。海洋生物の調査は、生物多様性の理解に不可欠であり、地球の生態系維持にも貢献します。また、研究室の先輩方、指導教員、職員の皆様の支援を受けながら、学内および実海域での実験を重ね、データの取得とともにAUV運用の経験を積んでいます。さらに、ミーティングでは多角的な視点から意見を交わし、得られたフィードバックを研究に活かしています。このような恵まれた環境のもと、充実した研究生活を送っています。

私は、可視光を用いて水中で無線通信を行う技術やその評価についての研究をしています。水中での可視光通信は、従来の音響通信やRF通信と比べ、高速・中距離・大容量という特徴を持ちます。水中で気中と同程度に自由な通信が可能になれば、より多様で効果的に海洋空間を利用することができます。そしてその実現には、可視光通信技術が欠かせないと考えます。また、研究以外では、研究室の先輩方や同期と共に、在学中の起業に向けて準備をしています。本専攻では、第一人者の先生方や多様な連携先、実験施設といった恵まれた環境下で研究に取り組め、学外でのチャレンジも歓迎されます。ぜひ私たちと一緒に海洋の研究に取り組みましょう!

大学院での進路を悩んでいた学部生の私に取り、数ある専攻と研究室の中から一つに絞るのは至難の業でした。決め手となったのはキャンパスや専攻、そして研究室の雰囲気です。展望がよく閑静な立地のキャンパスの中で、比較的少人数であるため距離が近く丁寧な指導をしてくださる専攻や研究室の先生方の指導を受け、自分の関心のあることを集中して研究し、実りの多く落ち着いた日々を送っています。研究としてはガスハイドレートの海底地層部での挙動の解明に取り組んでおり、最終的には二酸化炭素の安定貯留や国産天然ガスの生産を目指しています。日本には海洋開発の基盤となる海底油田のような安定した産業がないため、広大な排他的経済水域を生かし切れていません。海洋の利活用のためには風力や海底資源など異なる分野間の共創が必須であり、それに向けて多分野が集まる学融合的な海洋技術環境学専攻は今後の日本と世界を牽引する中核となります。この若く新しい専攻でともに研究できる日を楽しみにしています。

私はガスハイドレートを含む堆積物の形態と浸透率に研究の焦点を当て、自身の専門知識を拡張しガスハイドレート研究の進歩に貢献することを目指しています。 知識豊富で協力的な教授陣のサポートを受けて、定期的な打合せ、セミナー、ワークショップを通じて、研究を進めています。 さらに、東京大学の高い評判や奨学金・研究資金の提供は、私たちの研究経験をさらに充実したものにしてくれます。また、学業以外にも、将来のキャリアパスを形成する機会が豊富にあります。
自然環境は、日常生活と研究活動の双方において、絵のように美しく便利な背景を提供してくれますし、相互扶助が当たり前の友好的で協力的なコミュニティを育んでいます。 スポーツチームやハイキングといった共同活動に参加することで、一緒に過ごす時間はさらに楽しくなります。 留学生として、我が家のようにくつろげる環境がここにはあります。
要約すると、東京大学は大学院での学習と研究に優れた環境を提供しており、入学希望者にとって魅力的な選択肢です。
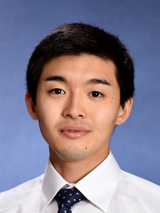
私は自律型海中ロボット(AUV)群のナビゲーション手法を研究しています。これにより、海洋資源の効率的な探査や海洋環境のモニタリングが可能となり、海洋学や海洋工学の分野での知見を深めることが期待されます。海洋調査は、持続可能な経済発展、責任ある資源の収穫、そして堅実な環境保護を追求するために不可欠な役割を果たしています。
私はカナダや国内の海中ロボット企業で研究開発に携わり、海洋ロボット技術の社会実装に向けて研究を深めるため、この専攻に入学しました。これまでに、和歌山市加太地区や神戸市須磨海づり公園の人工魚礁調査など、数々の実海域での研究を行っています。さらに、学会での発表などを通じて、世界中の研究者と交流する機会も多くあります。一緒に海洋技術の研究を進め、地球環境に配慮した人類発展の未来を築いていきましょう!
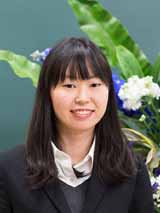
私は海洋環境に関心があり、本専攻の修士・博士後期課程へ進学しました。講義で学んだ知識が実践的に応用できることを実感するともに、最先端の深海化学センシング技術開発研究に携わりました。また、航海や交換留学、国際学会での発表など、国内外の研究者とのディスカッションの機会に恵まれました。
現在は引き続き研究者として海洋研究開発機構にて、 マイクロプラスチック汚染や気候変動による海洋環境変化をモニタリングする、オプティクス技術開発を行っています。環境問題解決の一端を担いたく日々研究に取り組む中で、これまでの経験や国内外に拡がる人脈の大切さを感じています。
本専攻では、海洋研究を通して学際的・国際的な視野を養うことができ、卒業後も生かされる知識・経験が得られることと思います。

私は日系ブラジル人で、サンパウロ大学で石油工学の学士号と機械工学の修士号を取得した後、東京大学で博士号を取得しました。新しいテーマや方法論に関する研究は常に挑戦的で、この専攻の博士課程でそれに取り組むための非常に良い環境に恵まれたのは大変幸運でした。 指導教員とOTPEスタッフのおかげです。
私は現在、国際石油開発帝石株式会社のCO2貯留グループに所属しています。1 年目ですが、これまでは石油産業に関する研修と、マレーシアでの火災危険訓練を含む実際の実習に焦点を当てていました(写真参照)。現在私は、二酸化炭素回収と貯留に関するシミュレーションに取り組んでいます。私の博士号は確実に私の現在の仕事の礎となっています。

海洋というフィールドと工学に興味があった私にとって本専攻は自分の興味に適していると考え、本専攻に進学しました。期待していた通り、本専攻では海洋における理学・工学的知見はもちろん、環境問題や海洋政策など幅広い分野にわたって学ぶことができました。また自らの研究の一環として長期にわたる極海域での観測航海に参加する機会や、研究発表として学会・研究集会等で国内外の研究者と討論する機会を得ることができ、知識を習得する以上に海洋について深く知り、考えることができました。
卒業後は船級協会に入会し、国内外の船舶の船級規則の制定やそれに基づいた審査、船舶・海洋構造物に関わる研究開発等に従事する予定です。本専攻で学んだ知識や経験を生かして、より良い海洋の利用と海洋環境の向上に業務の一環として貢献することができればと考えております。
本専攻は海洋という学際的な場での俯瞰的な知見と工学・環境学という専門性を同時に学ぶことができ、講義や研究活動、さまざまな活動を通して学内外で得がたい経験を得られる専攻だと思います。
Copyright© 2025
東京大学大学院新領域創成科学研究科
海洋技術環境学専攻
All Right Reserved.
Produced by coanet